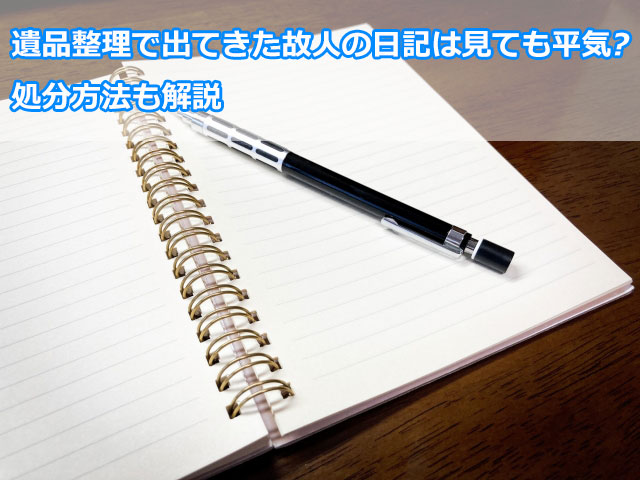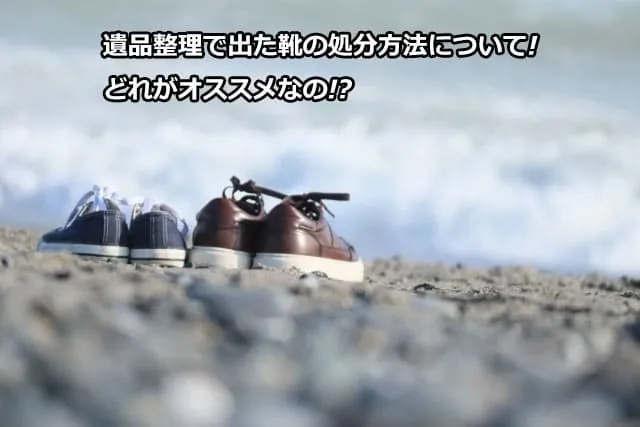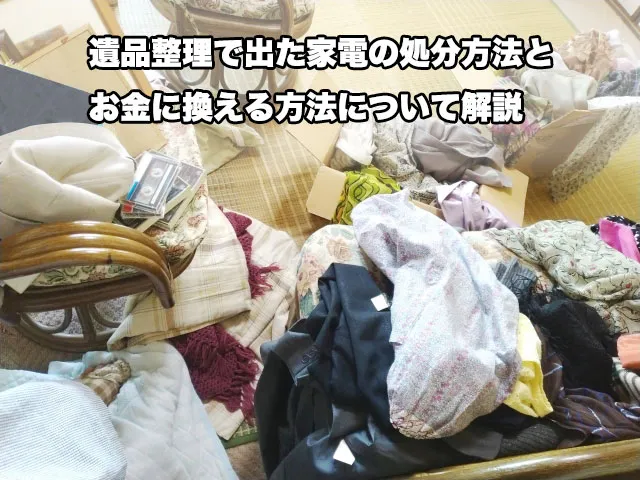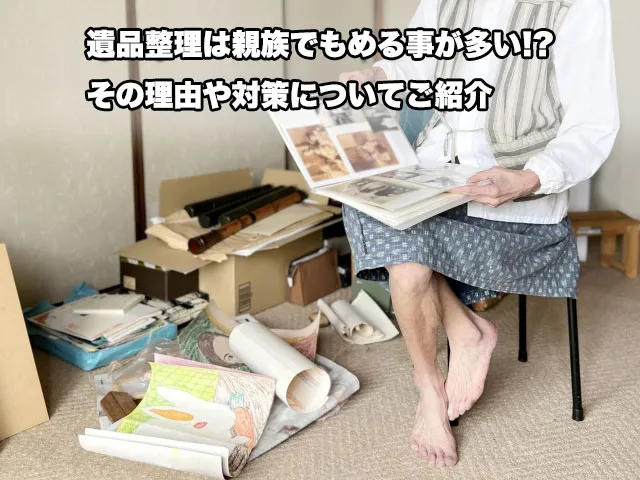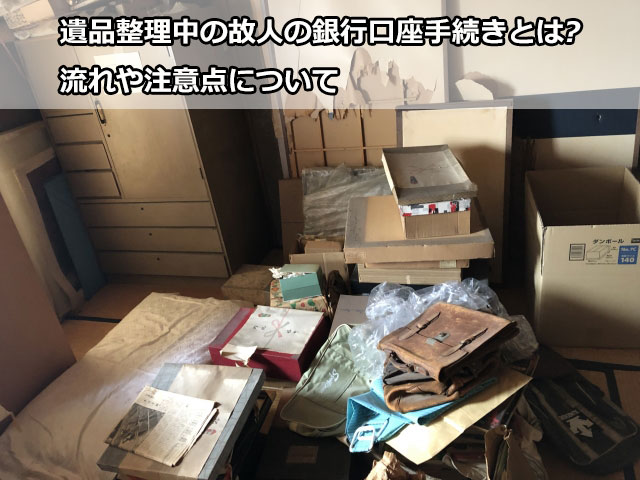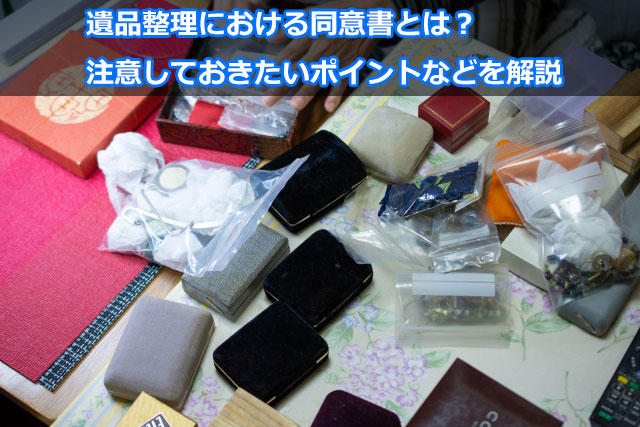遺品整理で出たレトルト食品の処分方法とは!?大量に残る理由も知ろう
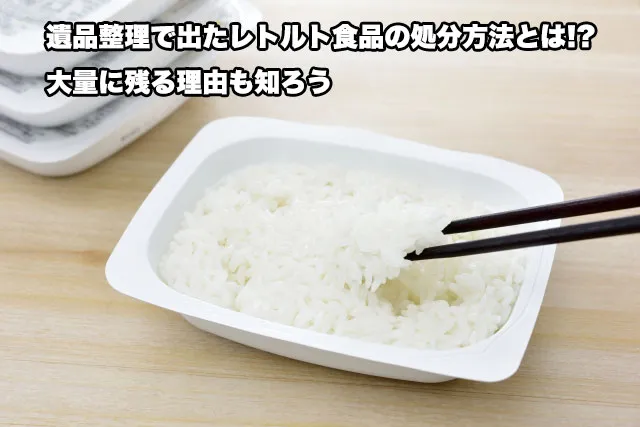
故人の遺した遺品を分別して適切に処分することを「遺品整理」と言います。
この作業中に大量に食料品が見つかることが多いです。
調味料をはじめ、レトルト食品やカップラーメンや冷凍食品など。
ご家族の方が遺品整理を行う際、こういった食品たちをどのようにして処分すべきか?
迷ってしまうというケースが多々あります。
そこで、本ページでは遺品整理で出たレトルト食品の適切な処分方法についてご紹介していきます。
合わせて、なぜ?大量に家からこういった食品が見つかってしまうのか?
その理由についても解説しています。
・遺品整理で出たレトルト食品の適切な処分方法がわかる。
・故人が大量にレトルト食品などをストックしている理由がわかる。
・フードロスしないための対策を知れる。
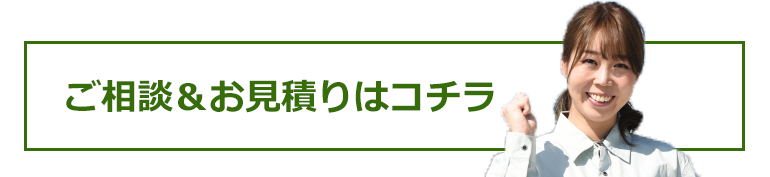
遺品整理で大量にレトルト食品が見つかる理由
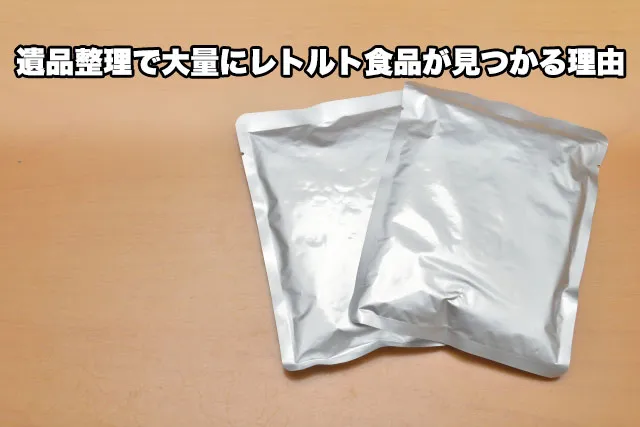
亡くなった方(以降、故人)の遺した遺品を整理することを「遺品整理」と言います。
ご家族の方で相続をする方が基本的に行う作業で、
相続の申告までには終わらせないといけないことです。
遺品整理中では、様々なものが発見されます。
貴重品などはもちろんですが、大きな家具や家電、大量の衣類や寝具など、
明らかに不要で処分しないといけないものも多いです。
その中で「レトルト食品」が大量に見つかるケースもあります。
では、何故大量に家の中に残されているのでしょうか?
その理由からご紹介していきます。
- 安売り時に買いだめしてしまう
- 体力的な問題
- 日持ちがするため
- つい忘れて大量に買ってしまう
- 勿体無くて捨てられない
安売り時に買いだめしてしまう
高齢者の一人暮らしの場合、なるべく食費を抑えようと考えて、
安売りの時には、大量に買っておく方が多いです。
家にどれだけのストックがあるかはそこまで把握しておらず、安いからといって大量に買ってしまう。
このようなことが増えていき、
家にあるレトルト食品の数がどんどん増えていってしまう方も多いです。
気づけば、レトルト食品だけで台所が埋め尽くされているなんて方も・・・
日持ちがするため、あまり深く考えずストックとしてどんどん買ってしまう方が多いのも事実です。
体力的な問題
高齢者の一人暮らしの場合、全ての生活を一人でこなさないといけません。
しかしながら、中々体がうまく動かないという方も多いです。
そういった際には、わざわざ料理するよりレトルト食品で済ませたいという方もいらっしゃいます。
こういった背景から、
普段からレトルト食品を購入して食べているという方も実は多いです。
これが家の中に大量にレトルト食品が残されている理由です。
日持ちがするため
レトルト食品は、消費期限が長いのが特徴です。
従って、安い時に買っておいていつ食べてもOKだと認識する食品です。
特にカレーなどはご飯の上にかけるだけで良いですし高齢者にとっても非常に楽です。
消費期限は長いですし、便利な食品ですが、
大量にストックしているとどんどん古いものが消費されずに、
気づけば消費期限が切れているなんてこともあります。
しかしながら、
レトルト食品だし、まだ食べると思って捨てずに残してしまう方も多いです。
これが遺品整理時に大量に見つかる理由の一つでしょう。
つい忘れて大量に買ってしまう
高齢者になると、認知症ではなくても少しずつ記憶が甘くなることもあります。
思い出そうとしても、正確に思い出せない。
このようなことが少しずつ増えていきます。
レトルト食品についても、
いつ買って、いつまで保つのかなどはしっかりと把握していないことも多く、
次から次へと購入していった結果、大量の消費期限切れのレトルト食品が見つかるのです。
勿体無くて捨てられない
高齢者の中には、幼少期から親に「捨てるのは勿体無い」ということを強く教わって、
育てられたという方も多く、消費期限が切れていても中々、捨てられないという方も多いです。
特に、レトルト食品の場合、
少しぐらい切れていても食べれるだろうと考える方も多く、
これが大量にストックして家の中から見つかる要因だと言えます。
遺品整理で出たレトルト食品の処分方法について
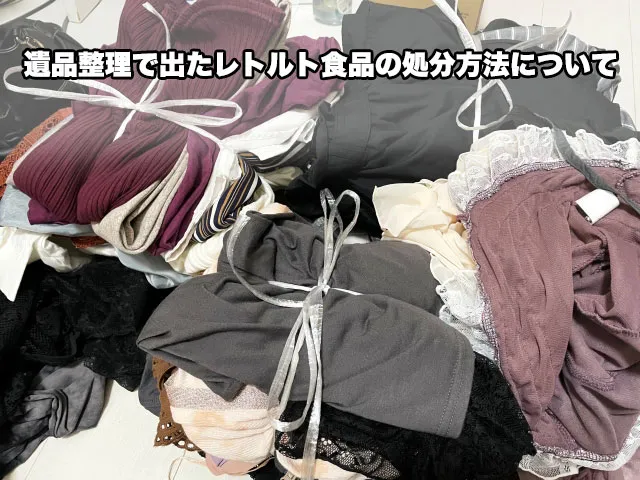
遺品整理で発見されたレトルト食品の適切な処分方法についてご紹介していきます。
誤った捨て方で迷惑をかけないように注意しましょう。
中身と容器を分けて処分する
レトルト食品の場合、様々な容器に入っていることが多いです。
まずは、容器の中から中身を取り出す必要があります。
中身を取り出す際には、
新聞紙やキッチンペーパーなどに出して、吸収させた上で家庭ごみとして処分します。
自治体によってルールが異なりますが、そのまま可燃ごみとして捨てることが大丈夫な場合もあります。
問題なのは、容器の方です。
レトルト食品に使われている容器は様々で、レトルトパウチの袋やプラスチック容器、缶詰などがあり、
これらは「資源ごみ」として分別する必要があります。
もちろん紙製の容器の場合には可燃込みでOKです。
しかしながら、容器が紙以外の場合にはよく確認した上で、
お住まいの自治体のルールに則って処分するようにしてください。
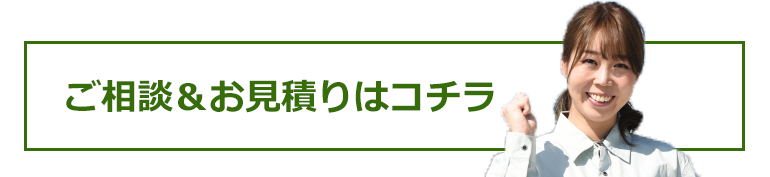
レトルト食品のその他の処分方法
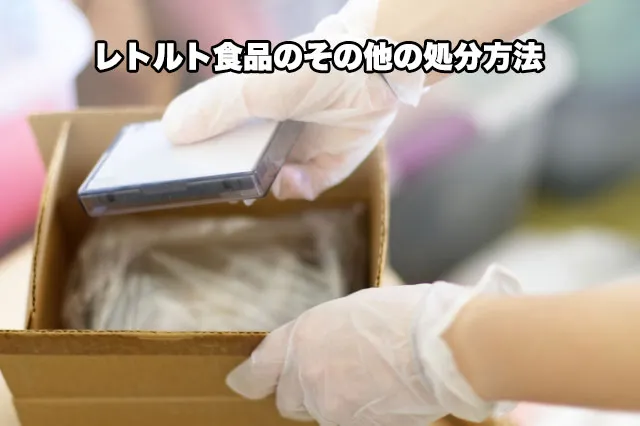
レトルト食品を可燃ごみとして処分する方法は一般的だと思いますが、
中には食べれるものを捨てるのは・・・と考える方もいると思います。
そういった方には、2つの方法から適切な処分を行えますので今からご紹介していきます。
- フードバンクなどに寄付する
- 自分達で食べる
フードバンクなどに寄付する
遺品整理で出たレトルト食品をフードバンクなどに寄付することで、
フードロスを防ぐことに繋がりますし、支援を必要とするご家庭などに届けることができます。
しかしながら、
どのような物でも寄付できるわけではなく、ある一定の条件などが設けられているケースが多いです。
まずはそういった条件などを確認することが大切です。
提供できるレトルト食品について
| 対象物 | 条件など |
|---|---|
| 常温保存ができるレトルト食品 | カレー、丼の具、スープ、パスタソースなど |
| 賞味期限が十分に残っているもの | か月以上(団体によっては2~3か月以上) |
注意点について
開封済みのレトルト食品、手作りの食品の寄付はNGです。
また、要冷蔵・要冷凍品は原則NGとなるほか、アルコール飲料はほぼ不可です。
また、パッケージが破損しているものについても提供ができません。
寄付の流れについて
- 1,近くのフードバンクや自治体、NPOに連絡して「寄付できる食品の条件」を確認する
- 2,持ち込みor宅配で送る
自分達で食べる
まだ食べられるものであれば、自分達で食べるという方法もあります。
この際、よく確認したいのが状態です。
まずは以下のようなことを確認しましょう。
- 1,賞味期限・消費期限を確認する
- 2,保存状態を確認する
- 3,保存場所などを確認する
もし、上記のような項目を確認した上で、
食べられそうなレトルト食品については自分達で食べることで、
フードロスを防ぐことができて、無駄な処分をせずに済むでしょう。
場合によっては、
知人などに配ることもあるかもしれませんが、そういった際には、
より一層、食べられるのか否かの判断は徹底しましょう。
遺品整理で出たレトルト食品における注意点
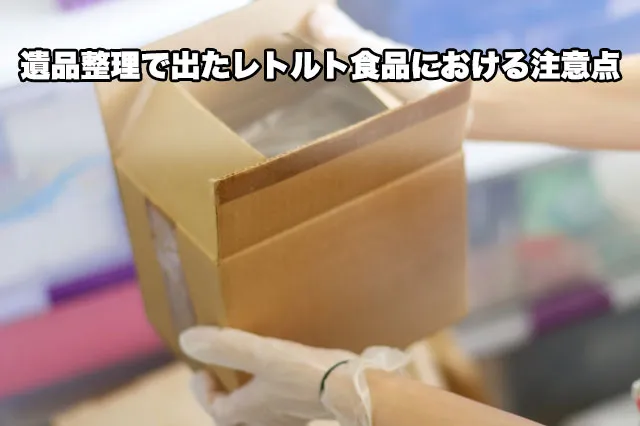
遺品整理で出たレトルト食品における注意点についてご紹介いていきます。
賞味期限と消費期限の違い
レトルト食品には、賞味期限または消費期限が記載されていると思います。
まずは、これらを確認した上で捨てるか否かを判断しましょう。
ちなみに、
賞味期限とは、おいしく食べられる期限のことであり、
消費期限とは、安全に食べられる期限のことを指します。
つまり、
消費期限が切れているレトルト食品については、そのまま処分をしてください。
問題なのが賞味期限が切れているレトルト食品です。
次項でご紹介していきます。
賞味期限が切れているレトルト食品の処分判断について
賞味期限が切れているレトルト食品については、
どのようなものでも「数週間〜1か月程度」は問題ない場合が多いです。
ただし、保存方法などによって変わります。
- 既に開封済みのもの
- 高音多湿な場所で保管されていたもの
- 匂いや色味が変わっているもの
上記のような場合には、いますぐに処分するようにしましょう。
ちなみに、
よくあるカップラーメンなんかは、1〜3か月くらい過ぎても問題ない場合が多いです。
しかしながら、処分する際にはよく確認することが大切です。
無駄なフードロスを防ぐために

高齢者の一人暮らしで無駄なフードロスを防ぐための方法をご紹介して行きます。
食品の管理状態を定期的に確認する
まずは、家の中の食品の管理状態を定期的にご家族の方が確認してください。
遠方に住んでいるという場合であっても、電話などをしながら、
今どのような状況にあるのかを確認してあげてください。
この際、以下のようなことに注目してください。
- まとめ買いより、使い切れる量をこまめに購入を指導。
- 食材を見えるように配置して、古いものから使うように指導。
- 賞味期限と消費期限の違いを教えてあげる。
まずは、いかに無駄なストックを増やさないかが大切です。
その上で、なるべく古いものから食べていくように教えてあげましょう。
さらに、
賞味期限と消費期限の違いがよくわかっていないケースもありますので、
違いを教えてあげて、フードロスを防ぐようにしましょう。
レトルト食品のフードロス防止チェックリスト
1.購入時
- 本当に食べる予定があるか確認してから買うようにする
- 家に同じ商品がどのくらい残っているか確認する
- 大量まとめ買いは「消費できる量」だけにする
2.保存時
- 賞味期限が近いものを手前に置く
- 保存場所を固定して「レトルト専用の棚・箱」を作る
- 高温多湿な場所で保管しない
3.管理
- 賞味期限をスマホやカレンダーに記載する
- 月1回はストック棚を点検する
- 賞味期限が半年以内のものを把握する
4.消費
- 普段の食事に1つ取り入れて消費する(ローリングストック)
- アレンジして飽きない工夫をする
- 早めに使い切る意識を持つ
5.寄付・活用
- 食べきれないと判断したら早めにフードバンク・地域団体に寄付する
- 友人・知人などにお裾分けする
埼玉県の遺品整理ならリンピアにお任せください
埼玉県をメインに特殊清掃・遺品整理を行なっているリンピアでは、
ゴミ屋敷や孤独死の現場の原状回復、また普通の清掃まで行なっています。
遺品整理では、不用品回収・買取も合わせて行う事ができますので、
何かお悩みがあれば、気軽にご相談ください!
ご相談や見積もりなどは無料で行なっています!
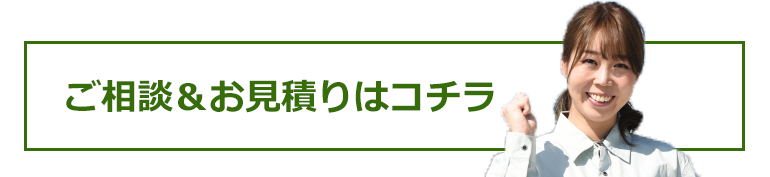
まとめ
本ページでは、
遺品整理で見つかったレトルト食品の処分方法についてご紹介して行きました。
最後に本記事の内容を再度、まとめておきます。
- レトルト食品は、可燃ごみとして処分できる。
- 処分する際には、容器と中身を分ける。
- フードバンクなどに寄付するという方法もある。
いかがだったでしょうか?
とても便利なことからレトルト食品を食べる方も多いと思います。
しかしながら、どれだけストックがあるのか?
いつまで食べられるのかなどを把握していないとフードロスの原因となります。
大量にフードロスを起こさないためにも、
生前から管理して、無駄を省くことが大切ですよ。

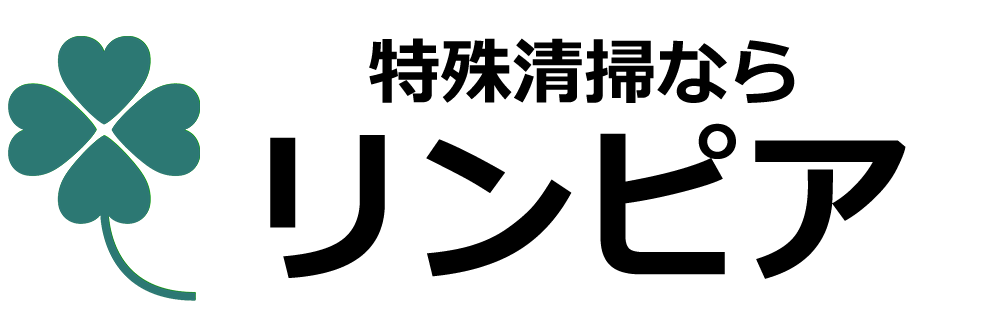
 無料お見積もり・ご相談はこちら
無料お見積もり・ご相談はこちら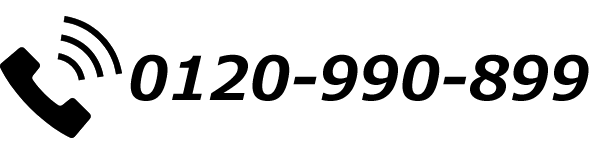
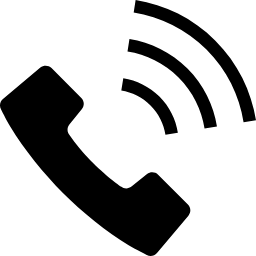 0120-990-899
0120-990-899